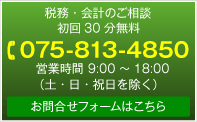かつて、音楽業界がそうであったように、
映像製作の現場がアナログからデジタルへ移行する波の中で、
カメラ・メーカーは、こぞってデジカメ(デジタルカメラ)へ
大きく舵を切ることになりました。
ところが、携帯電話にカメラ機能が搭載されると、
ユーザーのニーズは、デジカメから徐々に遠のくことになります。
高機能なスマホが登場すると、デジカメの魅力はなくなり、
一眼レフ等を除き、底の見えない不振に陥ってしまいます。
一方、写真フィルム・メーカーは、早くから写真フィルムの衰退を見据え、
多角化に力を注ぐようになります。
最大手の富士フイルムは、液晶パネル用光学フィルム、
化粧品、医薬品と次々に新規事業に参入し、
「化学メーカー」に変わりつつあります。
2000年代には、小型インスタント・カメラを発売し、
女子高校生に支持されたことで、ブームとなりました。
続いて、07年に韓国ドラマで使われたことが火付け役となり、
現在も中国や東南アジアでブームが続いています。
富士フイルムといえば、使い捨てカメラを発明したことで有名ですが、
「写真を撮る」、「写される」ということが、
現在のように身近なものになったのは、
使い捨てカメラの登場が大きく影響しています。
カメラは、精密な細工が多く、手先の器用な日本人にとって、
時計と並び称されるほど世界に誇れる技術でした。
それゆえ、カメラの家庭への普及は早く、
70年代頃までには一家に一台はあたり前になっていました。
しかし、その扱いは難しく、女性や子供には使いづらいものでありました。
その後、ピント合わせが不要なオートフォーカス機能がついた、
コンパクトカメラが販売されるようになりましたが、
まだまだ、大人(男性)や愛好者向けのイメージが強いものでした。
富士フイルムでは、それまでもカメラのコンパクト化や、
操作の簡略化に力を入れていましたが、
子供にも手軽に扱える商品が出来ないかと考えていました。
それよりも、メーカーとしてもっと多くのフィルムを売りたかったのです。
フィルムにレンズを付ければカメラになる。
カメラの原理に立ち返り、
カメラというものの発想を切替えて考えてみたのです。
カートリッジ式のフィルムにレンズを取り付けたカメラ、
カメラ部分もレンズもすべてプラスチック製のカメラが誕生したのです。
価格も、コンパクトカメラの10分の1程度に抑え、
手軽に購入できるようにしました。
奇抜な発想のカメラは、新聞や雑誌でもとりあげられ、一躍話題になります。
なにより、観光地や駅の売店で気軽に買うことができるようになったおかげで、
利用者は一気に増え、フイルムの販売も飛躍的に伸びたのです。
現在も、写真フィルム・メーカーが生き残っていられるのは、
こうした絶え間ない進化を続けているからではないでしょうか。
老舗である米コダック社も経営破たんし、競争相手がなくなった現在、
インスタント・カメラの業界で、思うがままに利益を享受していられるのです。