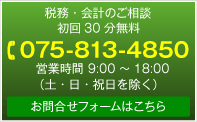コスプレ・アイドルの人気もさることながら、
簡単なコスプレ衣装なら手軽に手に入れることもできるようになって、
「仮装」へのハードルはかなり低くなってきていますね。
とろで先月末のハロウィーンでは、各地で様々なイベントが行われました。
テーマパークのハウステンボスでは、ハロウィーンの仮装パレードをはじめ、
舞台上のダンサーの振付に合わせて踊る「仮面舞踏会」、
ゴーグル型のモニターを使った「乗馬体験ゲーム」など、
来園者も参加できるイベントが満載で好評を得ているそうです。
夜には園内各所で壁面に立体映像を写す「プロジェクションマッピング」、
イルミネーションなど「光」をテーマにしたイベントも加わり、
お客を飽きさせないよう工夫を凝らしています。
イベント成功の陰には、テーマパークというハードより、
来園者の気持ちを高める点に力点を置いたことが挙げられます。
変ったイベントといえば、「ジュンク堂に住んでみる」というイベントには、
5600人の応募があり、当選した読書好きが1泊ツアーしたそうです。
ツイッターでのつぶやきがきっかけでしたが、
本屋という空間の楽しみ方をもう一度見直してもらうために開催したそうです。
「(紙媒体の)本や雑誌がスマホに負けてしまうのがもどかしい、
(本)棚をぼーっと眺めていると考えが浮かぶ。」と企画した店長は話しています。
大型書店では、従来許されなかった立ち読みや、
カフェ・スペースなどでの飲食も可能とされてきており、
本屋は特別な空間としての価値が高まってきています。
創業者の工藤恭孝氏が、父親が営んでいた書店の一部署を譲り受け、
開業したことがジュンク堂書店の始まりです。
大学は卒業したものの、就職先が決まらずぶらぶらしていた工藤氏は、
父親が経営していた書籍の取次会社に呼ばれることになります。
当時の書店は、駅前や商店街に店舗を構え家族で経営する、
いわゆる生業と呼ばれる小さな店舗がほとんどでした。
その書店を取引先とする取次会社も、
決して将来性があるとは言い難いものでした。
新しい試みとして、タバコ屋や雑貨店の店先にスタンドを置き、
雑誌を売る方法や、百科事典の月賦販売を始めました。
この方法は、子ども向け百科事典につながることとなり、
ベビーブームと重なって大ヒットすることになります。
やがて、大阪では紀伊國屋書店、旭屋書店と、
大型書店の出店が相次ぐようになります。
これからは大型書店の時代がやってくるとの思いから、
小売のために神戸に書店をオープンすることになり、
それが神戸・三宮1号店となります。
神戸の三宮を拠点に書店を展開していたジュンク堂書店は、
軒並み、神戸とその周辺の店舗が被災することになります。
震災を契機に、工藤氏は神戸を中心とした書店チェーンから、
積極的に全国書店チェーンを目指し事業展開を進めたのです。
地域の経済は大打撃を受け、競争力が弱った土地に、
競合が続々と乗り込んできたのです。
売上は大きく落ち込み、経営の維持、雇用を確保するためにも、
県外に売上を求める外に手が無かったのです。
時は経ち、今や脅威となる相手は同業ではなくなっています。
ネット通販が大きく力を伸ばし、電子書籍の普及も待ったなしの状態です。
本を買うお客が、書店を訪れるという前提はなくなり、
全てのお客のニーズを満たす書店経営は成り立たなくます。
書店の規模にかかわらず、来店するお客にターゲットを絞り、
それに合わせて、品揃え、店舗物件を選ぶ工夫が必要となります。