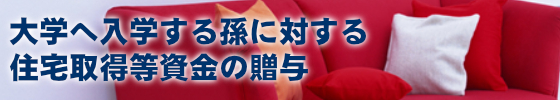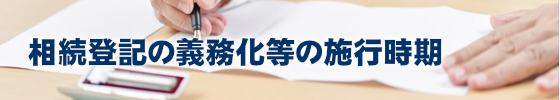
今回は相談事例を通じて、相続登記義務化の施行時期などについてご紹介します。

相続登記の義務化がスタートすると聞きました。具体的に、いつから何が変わりますか。
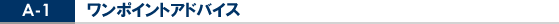
長年相続登記がされていないことにより、現在の所有者が不明となっている土地の問題を解消するために、不動産に関するルールが見直され、今般、施行日が定められました。相続登記に関連する改正については、2024年(令和6年)4月1日に施行されます。


1.相続登記の義務化(2024年4月1日施行)
相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
施行日よりも前の相続開始の場合についても、適用されます。2024年4月1日よりも前に相続人として所有権を取得したことを知っていた場合には、2024年4月1日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、遺産分割が3年以内に整わない場合は、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行った上で、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請をしなければなりません。
2.相続人申告登記(2024年4月1日施行)
①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、相続登記申請義務を履行したものとみなされます(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになります)。
この手続きは、所有権を取得したことを登記するものではありませんので、遺産分割が整った場合には、相続登記の申請が必要となります。
3.遺産分割に関する民法のルール変更(2023年4月1日施行)
相続開始から10年を経過した後にする遺産分割は、原則、具体的相続分(特別受益や寄与分を考慮した相続分)ではなく、法定相続分(又は指定相続分)によることとなります。
10年を経過した後であっても、相続人全員の合意があれば、具体的相続分による遺産分割(寄与分等を考慮して法定相続分と異なる分割をすること)を行うことは可能です。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。