
満期を過ぎた外貨建て保険の請求手続きと、課税上の取扱いを教えてください。
![]()
外貨建て養老保険に加入していた夫が、今年1月に満期を迎えた保険金の請求手続きを行うことなく、4月に亡くなりました。保険証券を確認したところ、死亡保険金の受取人は配偶者である私と長男、5割ずつ指定されています。
また、外貨で受け取ることができる旨の記載があるので、私も長男も外貨受け取りを希望しています。
満期が過ぎている契約ですが、死亡保険金として請求をするのでしょうか。
また、税金はかかりますか?
なお、相続人は、私(配偶者)、長男、次男の3人です。
- 保険種類:米ドル建て養老保険
- 契約期間:10年
- 契約者(保険料負担者):夫
- 被保険者:夫
- 満期保険金受取人:夫
- 死亡保険金受取人:配偶者・長男 各5割
- 死亡、満期保険金:200,000米ドル
- 全期前納保険料:175,000米ドル
![]()
ご相談の契約は、ご主人がお亡くなりになる前に満期が到来しているため、保険会社への請求手続きは死亡保険金ではなく、未請求であった満期保険金となります。この満期保険金は、ご主人の所得として所得税の課税対象となる他、ご主人の相続財産に加算します。また、所得税が課税されることにより納付すべき所得税が発生した場合は、相続税の計算上、ご主人の債務として遺産総額から控除できます。なお、申告上、外貨建ての財産は円建てに換算する必要があります。換算する際の為替レートは決められており、各々適用される為替レートは詳細解説にてご確認ください。
![]()
 保険金の請求手続きが被保険者の死亡後であっても、被保険者が死亡する前に満期を迎えていれば、死亡保険金としては扱われず、満期保険金としての請求手続きとなります。この満期保険金の課税の取扱いは、以下のとおりです。
保険金の請求手続きが被保険者の死亡後であっても、被保険者が死亡する前に満期を迎えていれば、死亡保険金としては扱われず、満期保険金としての請求手続きとなります。この満期保険金の課税の取扱いは、以下のとおりです。
ご相談の満期保険金は、満期が到来した年分のご主人の一時所得として、所得税の課税対象となります。実務上は、ご主人に代わり相続人が準確定申告を行い、納付すべき所得税が生じた場合には納付することとなります。
相続税の計算上、ご相談の満期保険金は、相続人共有の財産(未収入金)として、相続財産に加算します。死亡保険金ではないため、保険金の非課税制度(500万円×法定相続人の数)を適用することはできません。
また、(1)により所得税を納付することとなった場合には、その所得税は相続税の計算上、債務として遺産総額から控除できます。
外貨建て保険を外貨で受け取る場合、税金を計算する上では、円換算する必要があります。この際に適用される為替レートは、次のとおりです。
- 全期前納保険料:原則として払込日(保険会社受領日)のTTM(※)
- 満期保険金:原則として支払事由発生日(満期日)のTTM(※)
- 未請求であった満期保険金相当額:原則として支払事由発生日(死亡日)のTTB(※)
請求すべき手続きの放置期間が長くなるほど、証拠書類が探し出せずに手続きが煩雑になりがちです。他に手続きが放置されているものがないか、確認をしましょう。
相続に関するご不明な点は、当事務所へお気軽にご相談ください。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。







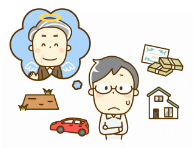 不在者財産管理人とは、不在者(妹様)に代わって財産を管理する人のことです。不在者が財産管理人を置いていない場合には、利害関係人は不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することができます(民法25条)。
不在者財産管理人とは、不在者(妹様)に代わって財産を管理する人のことです。不在者が財産管理人を置いていない場合には、利害関係人は不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することができます(民法25条)。
 贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で、居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭(以下、居住用不動産等)を贈与した場合、110万円の贈与税の基礎控除以外に最大2,000万円を控除することができる特例です。すなわち居住用不動産等については、最大2,110万円まで贈与税がかからずに贈与をすることができます。
贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で、居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭(以下、居住用不動産等)を贈与した場合、110万円の贈与税の基礎控除以外に最大2,000万円を控除することができる特例です。すなわち居住用不動産等については、最大2,110万円まで贈与税がかからずに贈与をすることができます。
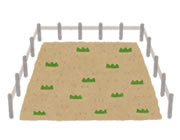 まず、土地の境界をはっきりさせます。具体的には、境界線が明確であるか否かを確認しましょう。もし明確でなければ、土地家屋調査士へ依頼し、確定測量を実施することで、隣接地との境界線を確定させることができます。
まず、土地の境界をはっきりさせます。具体的には、境界線が明確であるか否かを確認しましょう。もし明確でなければ、土地家屋調査士へ依頼し、確定測量を実施することで、隣接地との境界線を確定させることができます。
 契約者であり、被保険者である被相続人(ご主人)が特定の相続人であるご相談者様を受取人に指定しているときに、その受取人が死亡保険金を受け取る行為は、『保険契約に基づく行為』となります。
契約者であり、被保険者である被相続人(ご主人)が特定の相続人であるご相談者様を受取人に指定しているときに、その受取人が死亡保険金を受け取る行為は、『保険契約に基づく行為』となります。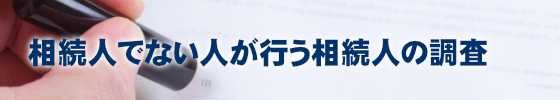
 あなたは義務なく事務の管理を始めた者(管理者)として、事務管理を行っていることになります(民法第697条)。
あなたは義務なく事務の管理を始めた者(管理者)として、事務管理を行っていることになります(民法第697条)。
 葬儀は、前もって準備万端、ということはまずなく、段取りや費用のことなど、悲しむ間もなくどんどん進めなくてはなりません。そのような中にあって多額の支払いが発生し、喪主の方が立て替え払いをすることは、よくあることといえます。
葬儀は、前もって準備万端、ということはまずなく、段取りや費用のことなど、悲しむ間もなくどんどん進めなくてはなりません。そのような中にあって多額の支払いが発生し、喪主の方が立て替え払いをすることは、よくあることといえます。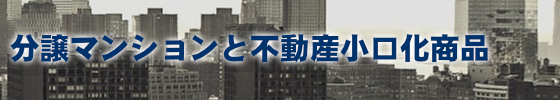
 不動産小口化商品とは、不動産特定共同事業法に基づき、複数の投資家から集めた資金にて収益不動産等を購入し、その不動産の運用収益を投資家に分配する商品です。簡単にいえば、分譲マンションの部分専有(区分所有)に対し、不動産小口化商品は全体共有ということになります。
不動産小口化商品とは、不動産特定共同事業法に基づき、複数の投資家から集めた資金にて収益不動産等を購入し、その不動産の運用収益を投資家に分配する商品です。簡単にいえば、分譲マンションの部分専有(区分所有)に対し、不動産小口化商品は全体共有ということになります。
 名義変更時点で課税はありません。
名義変更時点で課税はありません。
 相続の限定承認とは、相続人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという相続の方法です。
相続の限定承認とは、相続人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという相続の方法です。



