弊事務所の夏期休業日をご案内いたします。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
■休業期間
2017年8月11日(金)~2017年8月15日(火)
2017年8月2日
弊事務所の夏期休業日をご案内いたします。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
■休業期間
2017年8月11日(金)~2017年8月15日(火)
2017年7月20日

空き家を売却したときの特例について、適用するにあたり気をつけるべきポイントを教えてください。
![]()
親が住んでいた古い空き家を相続で取得しました。調べたところ、空き家を売った時の特例として儲けのうち3,000万円まで税金がかからない制度があることがわかり、この制度を利用できそうなのですが、知り合いから「適用できないこともあるらしい」との話を聞きました。相続時期や建物の建築年月日などは制度を適用するための要件,に合致しているのですが、その他の適用要件で気をつけないといけないことがあるのでしょうか。
![]()
適用するにあたって気をつけるべきポイントとして、たとえば被相続人が死亡直前にどこに住んでいたのか、があります。
![]()
○「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」の制度の概要
 この制度は、相続又は遺贈によって被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を売却したとき、一定の要件に当てはまるときは(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限る)、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる制度です。俗に「相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」、などとも言われています。
この制度は、相続又は遺贈によって被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を売却したとき、一定の要件に当てはまるときは(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限る)、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる制度です。俗に「相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」、などとも言われています。
「被相続人居住用家屋」とは、下記3つの要件全て当てはまるものをいいます。
この要件の中で、「主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物」とありますが、これは分かりやすく言い換えますと、「亡くなった方の生活の本拠であった不動産」となります、したがって、お亡くなりになる直前に、生活の本拠として施設等に入居していた場合には特例を受けることができない可能性があります。
例えば被相続人が亡くなる一年前から老人ホームに入居し、住民票等も異動していると、自宅であった不動産は「生活の本拠」とはみなされず、特例を受けることができなくなる場合が挙げられます。
この特例の適用を受けるために、確定申告時に「被相続人居住用家屋等確認申請書」を添付することになりますが、この申請書の添付書類に「被相続人の除票住民票の写し」が必要となり、この書類で生活の本拠であったかを判断されます。
建物の建築年月日や相続開始時期等が適用要件に合致していたとしても、「生活の本拠」であったことも、適用するための要件の一つです。ご留意ください。
なお、上記以外にも「売買代金が1億円以下であること」や、「土地建物で売却する場合、一定の耐震基準を満たすものであること」、「建物を壊して土地のみの譲渡」でも適用が可能であることなど、様々な要件がありますので、適用に当たっては当事務所にご相談ください。

申込書は提出したものの、保険料はまだ支払っていない保険契約を取り消すことはできますか?
![]()
3日前に、父(78歳)が銀行から生命保険を勧められ、家族の知らない間に契約申込書にサインをして提出しました。相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を確保するための保険、と担当者から説明を受けたそうですが、確認したところ、外貨建ての一時払終身保険で、為替変動があることも含め内容を理解していませんでした。
父は既に、非課税枠のために加入している生命保険(円建て)があります。それを失念しており、担当者に言われるまま手続きを進めてしまったようです。
あらためて家族で話し合い、父に確認したところ、契約する意向はないので取り消したいと言っています。今回、保険料はまだ支払っていませんが、既に契約申込書にサインをして提出しています。契約を取り消すことはできるのでしょうか?
![]()
生命保険は、申込書を提出してすぐに契約が成立するわけではありません。
通常、生命保険契約の成立には、一定の手続きが必要です。たとえば保険料の入金が必要な契約において、入金が未了であれば契約は成立していません。成立前であれば、速やかに取扱担当者に申し出ることで取り消すことができる可能性が高いです。
![]()
 生命保険契約の成立には、以下の手続きが必要です。
生命保険契約の成立には、以下の手続きが必要です。
また、クーリング・オフ制度を適用できる場合もあります。一般的には「クーリング・オフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い方から、その日を含めて8日以内であれば、書面により撤回できる」、とされています。ただし、保険会社によって規定が異なりますので、契約手続き時に渡される「注意喚起情報」「約款」に記載されている内容を確認する必要があります。
他方、以下のような契約についてはクーリング・オフの対象外です。
上記のほか、契約者が自分で窓口に出向いて契約をした場合や、自ら指定した場所で契約をした場合なども対象外となります。
告知(診査)が不要で簡易に契約手続きができる保険商品や、外貨建て商品において、高齢者が理解不十分なまま手続きを済ませ、後日、取り消したい等のトラブルに関する相談が増えています。無用なトラブルを避けるためにも、高齢者のご契約にあたっては提案内容の説明、契約手続きの際にご家族が同席されることをお勧めします。
なお、生命保険のご契約に関するトラブル等の相談は、一般社団法人生命保険協会で公平中立に受け付けています。そちらの窓口も活用できますので、ご検討ください。
2017年6月20日

今回は相談事例を通じて、不在者財産管理人についてご紹介します。
![]()
先日、母が他界しました。父は5年前にすでに亡くなっており、相続人は私と妹の2人だけです。母の相続財産は、自宅土地建物(評価額約2,000万円)と預貯金約2,000万円です。遺言書はありませんでした。私は以前から母の自宅に同居しており、今後もここに住み続けたいので、自宅土地建物は私が相続したいと思っています。不動産の登記名義を変更するには相続人全員による遺産分割協議が必要と聞きましたが、妹は10年程前から行方不明で連絡も取れず、協議をすることができません。どうしたらよいでしょうか?
![]()
本件の場合、家庭裁判所に妹様の不在者財産管理人の選任を申立て、選任された管理人と遺産分割協議をすることができます。
![]()
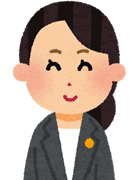 不在者財産管理人とは、不在者(妹様)に代わって財産を管理する人のことです。不在者が財産管理人を置いていない場合には、利害関係人は不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することができます(民法25条)。
不在者財産管理人とは、不在者(妹様)に代わって財産を管理する人のことです。不在者が財産管理人を置いていない場合には、利害関係人は不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することができます(民法25条)。
本件では、妹様が行方不明のため遺産分割協議ができないという利害関係がありますから、選任の申立てをすることができます。不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、本人に代わって遺産分割協議をすることができます。
不在者財産管理人には、利害関係のない親族等、または弁護士、司法書士等の専門家が選任されます。選任の申立て時に候補者を立てることができますが、必ずその候補者が選ばれるわけではありません。利害関係がある、財産が複雑、高額等の事情があれば専門家が選任される可能性が高いです。
なお、専門家が選任された場合、毎月の報酬や、遺産分割協議に係る報酬等が発生します。これらの報酬は不在者の財産から支払われます。また、不在者財産管理人の職務は、遺産分割協議が整っても終わらず、不在者が見つかったとき、亡くなったとき、財産が無くなったとき等まで続く点に注意が必要です。
2017年6月5日

土地の分割協議をするにあたり、何か注意しておいた方がよいことはありますか?
![]()
父の名義で下の図のような土地(合計900㎡)を所有しております。この度父が亡くなり、この土地をどのように分割しようか相続人3名(A、B、C)で遺産分割協議中です。分割協議にあたり、何か注意しておいた方がよいことなど、アドバイスを頂けませんか?
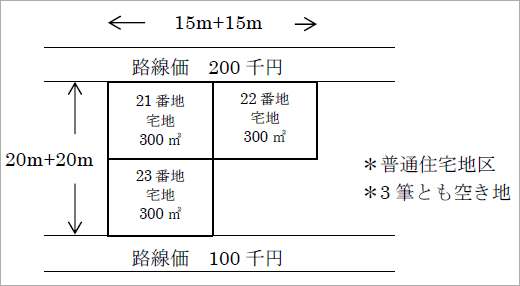
![]()
土地の相続税評価は、誰がどのように相続するかにより、評価額が大きく変わる場合があります。
![]()
土地の評価は、1.地目ごと、2.利用単位ごと、3.取得者ごと、に1つの土地として評価することになっています。したがって、必ずしも地番ごと(1筆ごと)に評価することにはなりません。
今回評価しなければならない土地について当てはめて考えてみますと、
21番地は相続人A、22番地は相続人B、23番地は相続人Cが相続する、という場合には、取得者ごとに相続することになっていますので、3筆を別々に評価します。
そこで、全体で評価する場合と別々に評価する場合とで、評価額がどのように変わるのか次で計算してみましょう。
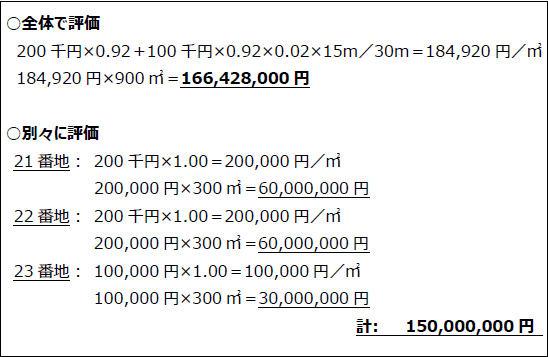
上記の通り、評価額の差額が16,428,000円も生じる結果となりました。適用される税率が20%の場合では、300万円程度納付する相続税額に差額が生じます。
ただし、利用の単位が同じ土地について取得者を分けて相続する場合には、その分割の合理性に配慮しなければなりません。例えば、下図のように高い路線価に面した部分のみをAが、その他をBが相続したような場合には、「不合理分割」と判定され、取得者ごとに別々に評価することは認められません。相続した部分が、それぞれ独立して有効利用可能かどうかが判断のポイントとなります。
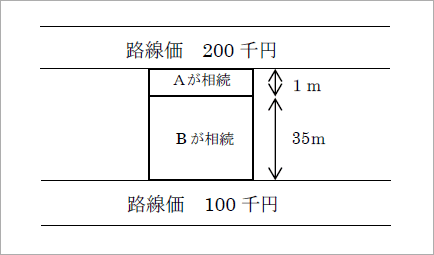
評価額の高い低いの判断のみでは分割協議はまとまりませんが、分割協議の内容によって納付する相続税額が大きく異なる結果となりますので、十分に検討する必要があるでしょう。
<まとめ>
<根拠条文> 財産評価基本通達7、7-2
2017年5月22日

平成29年の「地価公示価格」が発表されましたが、相続税などへの影響はあるのでしょうか?
![]()
先日、平成29年の「地価公示価格」が発表されたというニュースをみました。全用途の平均で地価は2年連続上昇したとありましたが、相続税などへの影響はあるのでしょうか?
![]()
全体的な地価の動向としては、三大都市圏では地価の上昇にやや一服感がみられる一方、地方四市(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)では三大都市圏を上回る上昇率を記録するなど、地価上昇は地方へ波及しています。そうはいっても、今回、41.3%の上昇率を記録した大阪・道頓堀を筆頭に大阪が全用途での上昇率トップ5を占めるなど、三大都市圏のもともと地価が高い場所がさらに上昇しているという傾向もありますので、7月に発表される相続税路線価についても、今回の地価公示の影響を受け、地価が大幅に上昇している地点の付近については相続税路線価も大幅に上昇し、相続税額にも影響を与える可能性があります。
![]()
 地価公示という制度は、地価公示法という法律に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示しているもので、主な役割としては以下のようなものがあります。
地価公示という制度は、地価公示法という法律に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示しているもので、主な役割としては以下のようなものがあります。
上記にあるように、地価公示価格は相続税評価や固定資産税評価の基準になるとされています。相続税や贈与税の申告にあたっては一般的に路線価等(いわゆる相続税路線価)が用いられますが、相続税路線価は、地価公示価格の水準の80%程度で評価されており、その均衡化・適正化が図られています。なお、地価公示価格、相続税路線価ともに毎年1月1日が評価の基準日とされていますが、地価公示の発表は例年3月の中~下旬、相続税路線価の発表は例年7月初旬となっており時間差があります。
今回の地価公示の概況をみてみましょう。全国平均では、全用途平均は2年連続の上昇となりました。用途別では、住宅地は昨年の下落から横ばいに転じました。商業地は2年連続の上昇となり、上昇基調を強めています。工業地は昨年の横ばいから上昇に転じました。三大都市圏をみると、住宅地は大阪圏が昨年の上昇から横ばいとなった以外、ほぼ前年並みの小幅な上昇を示しています。商業地は名古屋圏を除き上昇基調を強めています。工業地は総じて上昇基調を継続しています。地方圏をみると、地方四市(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)では全ての用途で三大都市圏を上回る上昇を示しています。地方圏のその他の地域においては全ての用途で下落幅が縮小しています。
国土交通省では、住宅地・商業地の用途ごとに地価の動向と背景を下記のように分析していました。ご参考ください。
2017年5月5日

財産債務調書に記載する生命保険の価額は、どのように算定すればよいのでしょうか。
![]()
確定申告時、顧問税理士から「財産債務調書を提出する必要があるかもしれないので、財産の価額を確認して欲しい」と言われました。生命保険についても確認するように言われましたが、生命保険の価額はどのように算定すればよいでしょうか?
![]()
ご相談の生命保険の価額、具体的には保険に関する権利の価額、定期金に関する権利の価額については、基本的にはその年の12月31日に生命保険を解約する場合に支払われることとなる解約返戻金の額とされています。ただし、保険会社等からその年の12月31日前の日において生命保険契約を解約する場合に支払われることとなる解約返戻金の額が分かる場合には、その解約返戻金の額を財産の価額として差し支えありません。
![]()
国税庁は、財産債務調書の提出制度(FAQ)(平成28年11月)の中で、次のように記しています。
| 【保険に関する権利の価額】 Q 生命保険に加入していますが、この生命保険の価額はどのように算定すればよいのですか。 なお、加入している生命保険契約は満期返戻金のあるものです。 (答) ただし、保険会社等から、その年中の12月31日前の日においてその生命保険契約を解約することとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額を入手している場合には、その額をその財産の価額として差し支えありません(通達6の2-9(13)イただし書)。 【定期金に関する権利の価額】 (答) ただし、保険会社等から、その年中の12月31日前の日においてその生命保険契約を解約することとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額を入手している場合には、その額をその財産の価額として差し支えありません(通達6の2-9(13)イただし書)。 |

解約返戻金の額は、契約されている生命保険会社の担当者、コールセンター、取扱代理店に照会することになります。保険会社によって照会に時間を要する場合があるようです。期日に余裕を持ってご照会なさるとよいでしょう。
また、保険会社から契約者へ年1回定期的に送付される「ご契約内容のお知らせ」には、解約返戻金の額が記載されていない場合がありますので、ご注意ください。 また、保険契約者向けのサービスとして、インターネットから解約返戻金の照会ができる生命保険会社もありますが、利用には登録が必要です。登録方法等は、保険会社から送付される案内や保険会社ホームページ等でご確認ください。
2017年4月20日

今回は相談事例を通じて、遺言の修正や撤回についてご紹介します。
![]()
私は以前、公正証書で遺言を作りました。財産の内容も変わったので、もう一度作り直したいと思っています。今回も必ず公正証書で作らなければならないのでしょうか。
![]()
既にある遺言を作り直すときに、前回と同じ要式で作る必要はありません。以前作った公正証書による遺言を自筆証書遺言によって作り直すことも可能です。
![]()
 遺言を作り直すことにより撤回という効力が生じます。遺言を撤回する際に、撤回する遺言の全文又は一部を特定した上で、これを「撤回する」と明確に記載することが望ましいといえます。
遺言を作り直すことにより撤回という効力が生じます。遺言を撤回する際に、撤回する遺言の全文又は一部を特定した上で、これを「撤回する」と明確に記載することが望ましいといえます。
明確に「撤回する」という言葉を用いなくても、以前作成された遺言と内容の抵触する遺言がされていれば、抵触する部分について撤回したものとみなされますが、撤回の意思を明確にするためにも、いつ作った遺言を撤回するかを明確にした上で、新たな遺言を作ると良いでしょう。
既に作成した遺言を全て撤回する方法だけでなく、一部を変更することも可能です。
【1】前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなします(民法1023条1項)。
【2】遺言と抵触する生前処分がされた場合には、抵触する部分について遺言を撤回したものとみなします(民法1023条2項)。
複数の遺言の内容が抵触する場合には、後の日付の遺言が優先されます。もちろん、後の日付の遺言が有効なものでなければ、撤回の効力は生じません。また、日付の異なる複数の遺言があった場合に、それぞれ遺言の内容が抵触しなければ、すべての遺言が有効となります。
遺言が残されていた場合、書いてある内容によって遺されたご家族が内容の解釈・判断に迷うケースがあります。大切なご家族のためにも、またきちんと希望を叶えるためにも、遺言作成時には専門家に相談することをお勧めします。
2017年4月5日

亡母名義の自宅を相続すると、相続税が安くなる特例が受けられると聞きました。どのような特例でしょうか?
![]()
1人で暮らしていた母が亡くなりました。母が住んでいた母名義の自宅を相続すると、相続税が安くなる特例が受けられると聞きました。どのような特例でしょうか?
![]()
ご相談の特例は、「小規模宅地等の減額特例」という制度です。
この制度は、亡くなった方がお住まいだった居住用の土地等を、一定の要件に該当する相続人が相続した場合には、その土地の評価について330㎡までの部分について評価額を80%減額できる、という特例です。
![]()
次の計算例で、減額できる評価額を計算してみましょう。
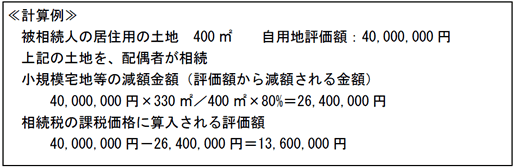
次に、ご相談の場合におけるこの制度の適用可否について、次のフローチャートで確認してみましょう。
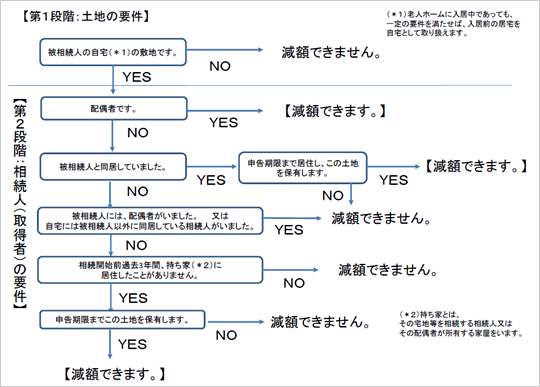
ご相談のようなパターン以外でも、この特例を受けることができる場合があります。
この特例は、要件を満たした土地等を、要件を満たした方が相続する場合に限り適用できます。誰がどの土地を相続するかによって、納める税金が大きく異なります。
相続発生後に要件を満たすための手当てはできませんので、事前に専門家と相談・検討するなどをし、適用要件の実態を整えましょう。
なお、居住用の土地以外に事業用等の土地についても、減額制度が設けられています。
<根拠条文> 措法69の4
2017年3月21日

引き継いだ家の相続登記をしていません。相続登記には相続税の申告のような期限がありますか?
![]()
3年前に母が亡くなったとき兄弟で話し合い、当時母と同居していた私が母名義の家を引き継ぎ、そのまま現在に至ります。ただし、相続登記はしていません。相続登記には相続税の申告のような期限がありますか?
![]()
相続登記を行うのに法令上の期限はありませんが、相続登記を行って権利を公に確定させると、その後の不動産の処分等の手続きはスムーズです。早めに相続登記を完了させることで、結果的に手続きが簡易になり、費用も抑えられます。
![]()
 法令上、相続税の申告は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行う必要がありますが、相続登記に期限はありません。そのため、そのまま放置していても法令上の罰則などはありません。ただし相続登記を済ませておかないと、法的な地位がなく公に権利を証明できないため、仮に当時合意していたとしても、将来的に他の相続人等ともめる可能性があります。また、相続した不動産を売却したいときや、相続した不動産を担保に銀行等から融資を受ける場合などの際の手続きが進みません。
法令上、相続税の申告は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行う必要がありますが、相続登記に期限はありません。そのため、そのまま放置していても法令上の罰則などはありません。ただし相続登記を済ませておかないと、法的な地位がなく公に権利を証明できないため、仮に当時合意していたとしても、将来的に他の相続人等ともめる可能性があります。また、相続した不動産を売却したいときや、相続した不動産を担保に銀行等から融資を受ける場合などの際の手続きが進みません。
その他、相続人が複数いる場合に不動産の相続登記をするには、遺産分割協議書が必要です。遺産分割協議書とは、相続人の間で遺産分割の協議をし、その内容を記した書類(実印押印、印鑑証明書添付)です。遺産分割協議書が作成されていなければ、不動産の相続登記ができないばかりか、口頭で遺産分割に同意した他の相続人が亡くなった場合、単独で不動産を取得するためには、さらにその相続人の協力が必要になります。
例えば、長男と三男の同意の上、次男が親の家を引き継いだ場合です。この場合、兄弟で遺産分割協議書を作成しない間に、長男に相続が発生すると、次男が親の家を単独で所有するためのハードルが上がります。なぜなら次男は、兄の相続人及び弟と親の家を自分が引き継ぐ内容の遺産分割協議書を作成しなければ、その家を単独で相続することができなくなるからです。兄弟の子世代(2世)であれば、交流は図りやすく意思疎通がしやすいため、遺産分割協議がまとまる可能性は高いと思われますが、兄弟の子世代(2世)に相続が発生すると、孫世代(3世)の同意が必要になってきます。孫世代までとなると交流が図りづらく権利関係が複雑化し、遺産分割協議は一筋縄ではいかない可能性が高まります。