ディーゼンエンジンをはじめとする発動機、
農業・建設機器、船舶を扱うヤンマー(ヤンマーホールディングス)。
同社は、全5話完結となるオムニバスストーリーとなる
オリジナルアニメを制作し4月からテレビで放映しました。
本格的なアニメ作品を作った理由のひとつは、
売上が伸びている海外展開を進めるためです。
「人の可能性を信じ、人の挑戦を後押しする」という価値観を発信し、
グローバルなブランドプロモーションを図ります。
また、アニメ作品のキャラクタービジネスを展開することです。
関西地方では、ヤン坊マー坊が紹介する天気予報のCMが、
長い間流れていました。
今後、このようなキャラクターを活用し事業として成立させます。
創業者である山岡孫吉氏が幼い頃から丁稚奉公に出る苦労をし、
ガス会社の工事作業員に雇われたことがきっかけで、
この道に進むようになります。
時代は、大阪市内にガス管の敷設が進み、
工場などはそれまでの蒸気機関から、ガスへ切り替えが進む最中でした。
蒸気機関は、広い据付場所が必要なうえに、操作も難しいものでした。
便利さから、ガスの普及が進むにつれて、
小さな馬力の動力を使っていた町工場や、
豆腐屋までガスに乗り換えるようになりました。
たまたま、工事に出かけた会社の倉庫で、
売れ残りのガス用ゴム管の山を目にします。
理由を聞いてみると、海外から輸入されているゴム管が、
輸送途中に劣化してしまい、ガス会社に納品を断られたというのです。
そこで、売れ残りのゴム管を売りさばく手伝いをはじめたところ、
在庫はきれいに処分できたのです。
山岡氏は、その手数料として手にした資金をもとに、
ゴム管の販売とガスレンジの修理業として商売を始めます。
その後、動力用エンジンの販売などを行っていましたが、
商品を右から左へ流すだけの商売には、嫌気がさしてきました。
お客に誇れるような製品を作り、胸を張って値段をつけられるような、
仕事がしたいと考え、発動機の製作を手がけるようになります。
農業用の、もみすり機、動力精米機、
水揚げポンプなどを製作して販売を始めます。
ある時、ドイツで初めてディーゼルエンジンを目にし、
あまりに優れた性能に、その虜になってしまいます。
その後は、とりつかれた様にエンジンの研究に没頭していくようになります。
2年がかりで、念願のディーゼルエンジンを完成させ、
現在の礎を築くことになるのです。
ヤンマーは、何処にも引けをとらない製品を作るという精神から、
84年から南極にある昭和基地の発電機用として、
ディーゼルエンジンを送り出しています。
極寒のうえ、絶対に止めることは許されない使命を受ける姿勢は、
その自信の表れといえます。






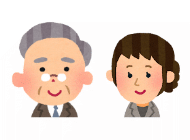 死後認知について、「子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。」と規定されています(民法787条)。
死後認知について、「子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。」と規定されています(民法787条)。 普通養子縁組とは、実際の血縁(いわゆるDNA)上の親子関係がない間柄において、法律的に親子関係を成立させる手続きの1つです。
普通養子縁組とは、実際の血縁(いわゆるDNA)上の親子関係がない間柄において、法律的に親子関係を成立させる手続きの1つです。



