
相続させない方が良い不動産があれば、教えてください。
![]()
不動産を多数所有していますが、相続させない方が良い不動産があれば、教えてください。
![]()
相続させない方が良い不動産として、相続税評価額が実勢価格を上回るもの、管理が困難なもの、値下がりが予想されるもの、などが考えられます。これらは相続に適さないため、生前に処分するなどの対策が望まれます。
![]()
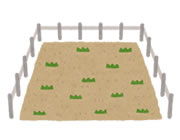 相続税を計算する際の不動産の評価額(以下、相続税評価額)は、実際に取引される価格(以下、実勢価格)より低くなる場合が多く、相続税の計算をする上においては、現金を持っているよりもメリットがある資産と考えられています。
相続税を計算する際の不動産の評価額(以下、相続税評価額)は、実際に取引される価格(以下、実勢価格)より低くなる場合が多く、相続税の計算をする上においては、現金を持っているよりもメリットがある資産と考えられています。
しかし、以下のような不動産は相続税を計算する上ではデメリットが多く、相続させない方が良いと一般的に考えられています。
- ○相続税評価額が実勢価格を上回っていると思われる不動産
- 住宅用地等としての需要が少なく、相続税評価額を下回る価格でしか売却できない地域の土地
- 個別要因による実勢価格の減少額が、相続税評価額を計算する上で減額できる額を大きく上回っている土地
- 道路や隣地との高低差が激しい土地
- 間口が狭い、不整形等により建築が困難な土地
- 過去に事故等(自殺・殺人事件等)があった又は近隣に嫌悪施設がある不動産
- 相続税評価額が実勢価格を大幅に上回っている次のような建物(主に鉄骨造又は鉄筋コンクリート造)
- バブル期等、建築費が高い時期に建てられた豪華な建物
- 規模の割に収入が少ない賃貸建物
- 利用が困難な建物(建物取壊しにより価値が上がる不動産)
- 地代が低額である昔からの貸地(底地)
- ○次の世代による管理が困難と思われる不動産
- 稼働率が低い賃貸不動産
- 大規模修繕等、建物のメンテナンスがほとんど行われていない不動産
- 遠方にある未利用不動産
- 建物が旧耐震基準である未利用又は賃貸不動産(取壊し予定の場合を除く)
- ○値下がりが予想される相続後売却予定の不動産
- バブル崩壊後値下がり続けて、上昇傾向がみられない売却予定の不動産
- 賃料水準の低下が著しい売却予定の賃貸不動産
- ○相続の争いの原因となりそうな不動産
- 全財産の中で大半の価値を占めている不動産
- 相続により取得することを嫌がられる不動産
これらの不動産を所有されている方は、早期の売却を検討されると良いでしょう。
ただし、“相続させない方が良い不動産”は、買い手からみると“買わない方が良い不動産”に該当しますので、売却できない又は売却にかなりの時間を要する可能性があります。
売却検討の際、売却が困難であるとすぐに諦めるのではなく、“相続させない方が良い不動産”を“相続させても良い不動産”に転換できるよう、実行可能な対策を講じていただくと良いでしょう。
なお、売却益を期待して購入した山林は、現在のところ売却を含め有効な対策が見つからない状況であり、“相続させるしかない不動産”といえます。このような状況にならないよう、不動産投資を行う前に、当事務所へご相談ください。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。







 夫の相続対策を検討している中で、保険会社から次の提案を受けました。これはその次の相続(二次相続)も見据えて、妻である私も生命保険に加入した方がよいというものでした。この提案はどのような効果があるのでしょうか?
夫の相続対策を検討している中で、保険会社から次の提案を受けました。これはその次の相続(二次相続)も見据えて、妻である私も生命保険に加入した方がよいというものでした。この提案はどのような効果があるのでしょうか?



