友人の影響もあって、高校生になってすぐに洋楽に関心を持つようになり、
私にとって、音楽は欠かせないものとなっています。
さらに、多くの人と同じように楽器にも手を染めることになりますが、
デジタル・シンセサイザーが普及する前であり、
当然、ナマ(アナログ)音が中心で、電子音といえばチッポケな音でした。
その後、爆発的な勢いでデジタルの波が押し寄せ、
音楽を演奏する側にも、切り離すことができない存在となりました。
今では驚くことにスマホのアプリでさえ、サンプリングで取り込んだ、
ナマ音の音程を調整することや、タイミングのズレを簡単に修正できます。
まるで、プロが使う機器で操作しているが如く、
手元の操作だけで、演奏のレベルが上がっていきます。
こんな事を体験すると、なるほどアイドル・グループや
Kポップ・グループの歌のレベルが高い理由も納得できてしまいます。
シンセサイザーをはじめとするデジタル楽器が、このように普及したのは、
統一した規格が決まっているからです。
2013年のグラミー賞では、「MIDI」という演奏情報を伝送する規格を定め、
音楽産業の発展に貢献として、音楽機器メーカーのローランドの創業者
梯 郁太郎氏にテクニカル賞が与えられています。
ローランドは、音楽好きであった梯氏が、自身の夢を叶えるため、
楽器作りをはじめたことが、その始まりになります。
若くして結核を患い長い療養生活の後、職探しをしたものの見つからず、
諦めて自ら電気製品の小売店を開くことにしました。
ある時、電子オルガンに興味を惹かれ、仕組みを調べてみると、
案外、簡単に作れそうに思えてきました。
「電気屋は楽器のことがわからない、逆に楽器屋は電気の事を知らない」
このことを解消できれば、大きなビジネスに結びつくかも知れない。
そう思うと、居ても立ってもいられない気持ちに駆り立てられ、
日本で最初の電子オルガンを送り出したい願望がふつふつと湧いてきました。
資本を仰ぐため共同で会社を設立して、電子オルガンの製造を始めますが、
新しい製品であるだけに取引が少なく、苦しい経営を強いられることになります。
暫くして、需要のあるギターアンプに製造を切り替えたところ、
折からのグループサウンズのブームにより、
若者の間にはエレキギターが大流行します。
当然の事ながら、ギターアンプも飛ぶように売れ、
事業は一気に拡大することになるのです。
しかし、共同経営者との意見の食い違いから、この会社を飛び出し、
新しくローランドを立ち上げて、再出発をすることになるのです。
いちから出直しのため、
ギターアンプやリズム楽器を手がける事からはじめます。
売り先も作り方もわかってはいましたが、お金が無いため派手な営業はできず、
現金取引の約束で値引き販売しコツコツと事業の足元を固めていったのです。
しかも、自転車操業が続く中、2年目にはシンセサイザーを完成させ、
5年後には世界に先駆けギターシンセサイザーを世に送り出したのです。
「名職人は、良い経営者になれず」
経営とは、妥協なくして成り立つことはありえません。
作品(仕事)の出来具合に固執するあまり、
妥協することを拒むと経営としては立ち行かなくなります。
経営が上手くいっていないと思ったときは、
あっさりと売れている形を取り入れることが一番の方法です。
「人よりいい物を売りたい」「人と違ったものを売りたい」
そんな気持ちは、一旦抑えて素直に「買って貰う」ことに徹しましょう。






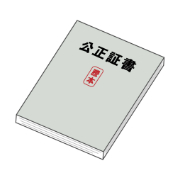 公正証書とは、契約を成立させるため等一定の事項について、公証人が公証役場で作成する公文書をいい、賃貸契約書等のような私文書に比べ、証明力や執行力が優れているという特徴があります。
公正証書とは、契約を成立させるため等一定の事項について、公証人が公証役場で作成する公文書をいい、賃貸契約書等のような私文書に比べ、証明力や執行力が優れているという特徴があります。 保険会社の多くは、生命保険の死亡保険金の受取人の範囲として、「被保険者の戸籍上の配偶者および2親等内の親族(血族)」と定めています。ただし、保険会社によっては個別事情の詳細を報告することで、内縁関係にある者、婚約者、共同経営者など一定の者の指定を認める場合もあります。
保険会社の多くは、生命保険の死亡保険金の受取人の範囲として、「被保険者の戸籍上の配偶者および2親等内の親族(血族)」と定めています。ただし、保険会社によっては個別事情の詳細を報告することで、内縁関係にある者、婚約者、共同経営者など一定の者の指定を認める場合もあります。



