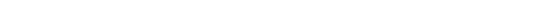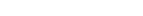お正月の前後1ヶ月の間、テレビ番組を見ていると、
日ごろ見たことのない会社のCMを目にすることが無いでしょうか。
この時期は、CMの放映料金が安いからかなと思っていましたが、
理由はそれだけではないようです。
大変失礼ですが、会社の規模に関係なく、これまで知らなかった社名ばかり。
そして、一般消費者には日頃接することが少ない、
製造業や建設業が多いのです。
そんな、村田製作所のCMもずいぶん長く放送されています。
どうして村田製作所が正月にCMを多く流すかというと。
過去に、社員が帰省した際、「○○製作所」という社名から、
町工場に勤めていると勘違いされ、気まずい思いをしたことが多くあり。
知名度を上げることを考慮してのことだそうです。
京都にある電子機器メーカーの村田製作所は、
セラミックコンデンサーの分野では世界に屈指のシェアを誇る会社です。
創業者である村田 昭氏が家業の陶磁器類の焼き物製作を引き継いだ時には、
一般的な陶磁器や絶縁体に使う碍子を作っていました。
戦時下における政府の統制により、同業者を集めてひとつの会社とする
企業合同体制を敷かれていたときのことです。
財閥系のメーカーから、特殊陶器を製作する依頼が入ってきたのですが、
業界が伸びるチャンスと見る村田氏に対して、
他の同業者は首を縦に振る気配がありませんでした。
そこで、手持ちのお金をはたいて工場を借り、
単独でその注文の製作に取り掛かったのです。
しかし、陶器を焼くための燃料の調達に手をこまねいている間に、
メーカーから返ってきたのは「別に工場を作ってしまった」とツレナイ返事でした。
その代わりに紹介されたのが、セラミックコンデンサーの製作だったのです。
その時に知り合ったのが、京都大学のある助教授でした。
終戦後の混乱期の中で、売れるものは何でも作り、
その日を食いつなぐのが精一杯の時期でした。
助教授も研究費を捻出するため、
簡単な電気製品を作るアルバイトのようなことをしていたのです。
そこで、研究応援する代わりに、セラミックコンデンサーの開発に
協力してもらう様申し入れをします。
まもなくして民間ラジオ放送の開始により、
コンデンサーを多く使うラジオが普及し、
村田製作所は電子機器メーカーへと礎を築いたのです。
企業の草創期における出会いは、事業が大きく変化するきっかけとなります。
出会というのは、人の結びつきもそうですし、手がける商品の場合もあります。
特に、人との出会いは、お互いの良さを引き出す「触媒」の役割を果たし、
決して一人では成し得なかった、大きな実りをもたらすことになるのです。



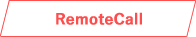


 建築基準法では、建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合において、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならないと定められています。
建築基準法では、建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合において、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならないと定められています。 生命保険の契約内容は、基本的に「保険証券」に記載されています。この「保険証券」は、契約が成立した後、保険会社から契約者に送付されます。この「保険証券」以外にも、契約後、保険会社から年1回届く「ご契約内容のお知らせ」でも、おおよその内容を確認することができます。
生命保険の契約内容は、基本的に「保険証券」に記載されています。この「保険証券」は、契約が成立した後、保険会社から契約者に送付されます。この「保険証券」以外にも、契約後、保険会社から年1回届く「ご契約内容のお知らせ」でも、おおよその内容を確認することができます。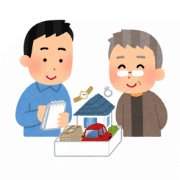 成年後見制度は2つに分けることができます。
成年後見制度は2つに分けることができます。 不動産投資は多額な資金が必要で、一投資家のみで投資するには難しい場面があります。そこで、持分を分割(小口化)することで、投資しやすい商品として取引が可能となります。このような仕組みを利用した金融商品を、不動産小口化商品といいます。
不動産投資は多額な資金が必要で、一投資家のみで投資するには難しい場面があります。そこで、持分を分割(小口化)することで、投資しやすい商品として取引が可能となります。このような仕組みを利用した金融商品を、不動産小口化商品といいます。
 2024年4月1日より、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければならなくなりました。これは法律で義務化されたため、一般的に「相続登記の義務化」といわれています。
2024年4月1日より、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければならなくなりました。これは法律で義務化されたため、一般的に「相続登記の義務化」といわれています。 生命保険の死亡保険金受取人は、生命保険の契約申込時に契約者が指定します。
生命保険の死亡保険金受取人は、生命保険の契約申込時に契約者が指定します。