
生命保険契約が「失効」すると死亡保険金を受け取ることができず、相続税の保険金の非課税の適用も受けられません。
![]()
夫が亡くなり、生命保険について確認したところ、保険料をしばらく払わずに放置していた契約が見つかりました。
保険会社へ問い合わせたところ、「『失効』しているため死亡保険金は支払われない。解約返戻金があるので相続人の方で所定の請求手続きをとってください。」といわれましたが、よく理解できませんでした。
「失効」とはどのような状態なのか、また、相続においてどのように扱われるのか教えてください。
- <生命保険契約の内容>
- 契約者(=保険料負担者):夫
- 被保険者:夫
- 保険種類:終身保険
- 死亡保険金受取人:妻
- 死亡保険金額:1,000万円
- 解約返戻金:200万円
![]()
「失効」は、契約の保障が切れた状態をいいます。この場合に支払われる解約返戻金は相続財産となり、相続税の計算上、保険金の非課税の適用はなく、全額が課税対象となります。
![]()

生命保険は保険料を支払わずに所定の猶予期間が経過すると、保険料自動振替貸付制度(※1)が適用されていない限り、保障の効力が切れます。これを「失効」といいます。
「失効」状態では保障の効力を失っているため、死亡保険金(ご相談のケースであれば1,000万円)を受け取ることはできません。解約返戻金があればこれを請求することはできますが(ご相談のケースでは200万円)、解約返戻金は死亡保険金とは異なり、他の資産と同じように相続財産として扱われ、遺産分割の対象になります。
また、「失効」状態では死亡保険金受取人の権利も消滅しており、死亡保険金受取人が誰に指定されていたかは関係ありません。
上述のとおり、解約返戻金は相続財産となるため、相続税の計算において課税対象となります。
また、解約返戻金は死亡保険金ではありませんので、相続税の計算上で非課税となる「500万円×法定相続人の数」を適用することはできません。
契約が有効中に保険料が未払いとならないよう、保険料自動振替貸付制度(※1)を付加するなど、払込方法(経路)を変更することで、「失効」にならないようにする方法もあります。
また、どうしても保険料の支払いが困難になったときは、減額(※2)、払済保険への変更(※3)、延長定期保険への変更(※4)などにより、意向にあわせた見直しを検討できる場合もあります。
ただしこれらについては、保険会社や保険種類、解約返戻金の金額等により対応できない場合もあります。できるかどうかは、保険会社へご相談ください。
せっかく相続対策のために契約しても、保険料を払い忘れて「失効」させてしまうと目的を果たせなくなります。被保険者が生存中であれば、未納分の保険料を支払い、かつ、健康状態について所定の手続きをとって要件をクリアすることにより契約が復活できるケースもありますが、相続発生後に復活させることは不可能です。生命保険は、加入時だけでなく加入後も、保険料の支払いに無理はないか、見直した方がよい点はないか、など定期的に確認をしながら、状況にあわせた無理のない契約にすることが「失効」しない、最も大切なポイントといえるでしょう。
- (※1)保険料自動振替貸付制度
保険契約を有効に継続するために、解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に保険会社が立て替える制度。
… 立て替えられた保険料には保険会社所定の利息が付きます。 - (※2)減額
保険金額を減らすこと。
… 保険金額を減らした分、保険料の負担は軽くなります。 - (※3)払済保険への変更
保険料の支払いを中止して、その時点の解約返戻金をもとに保険期間を変えずに保障額の少ない保険に変えること。
…付加している特約は消滅する点に注意しましょう。 - (※4)延長定期保険への変更
保険料の支払いを中止して、その時点の解約返戻金をもとに保険金額を変えずに死亡保障だけの定期保険に変えること。
… 保険期間が短くなることもあります。付加している特約は消滅する点にも注意しましょう。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。







 この遺言の場合、「任せる」と書かれていますが、「任せる」の意味は、「①するがままにしておく。放置する。②相手のするままになる。さからわず、なされるがままでいる。ゆだねる。③他の人に代行してもらう。委任する。④下襲の裾などを後ろに流れ引くままにする。⑤従う」です(広辞苑より)。任せるという言葉には渡すという意味が含まれておりませんので、この遺言の文面から、お父様が土地を渡したいという意思を読み取ることが可能かどうか、ということになります。
この遺言の場合、「任せる」と書かれていますが、「任せる」の意味は、「①するがままにしておく。放置する。②相手のするままになる。さからわず、なされるがままでいる。ゆだねる。③他の人に代行してもらう。委任する。④下襲の裾などを後ろに流れ引くままにする。⑤従う」です(広辞苑より)。任せるという言葉には渡すという意味が含まれておりませんので、この遺言の文面から、お父様が土地を渡したいという意思を読み取ることが可能かどうか、ということになります。
 弔慰金とは、被相続人の雇用主などが、亡くなった従業員を弔い、遺族に対して慰めの気持ちを込めて渡すお金で、退職金とは別に支払われるものをいいます。
弔慰金とは、被相続人の雇用主などが、亡くなった従業員を弔い、遺族に対して慰めの気持ちを込めて渡すお金で、退職金とは別に支払われるものをいいます。
 「買取」と「仲介」について、それぞれのメリット、デメリットを中心に以下、解説いたします。
「買取」と「仲介」について、それぞれのメリット、デメリットを中心に以下、解説いたします。
 一時払い終身保険とは、一生涯保障が続き、加入時に一括で保険料を支払う保険です。この一時払い終身保険の相続対策としての効果と注意点について、以下、解説いたします。
一時払い終身保険とは、一生涯保障が続き、加入時に一括で保険料を支払う保険です。この一時払い終身保険の相続対策としての効果と注意点について、以下、解説いたします。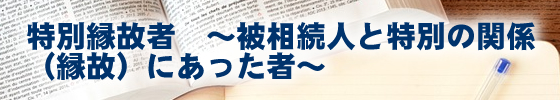
 相続人が不存在の場合、原則として亡くなった方の財産は国庫に帰属します。しかし、家庭裁判所の審判により特別縁故者と認められることによって、その財産を取得することができます。特別縁故者とは、「被相続人と特別の関係(縁故)にあった者」を指し、その範囲は次の通りです。
相続人が不存在の場合、原則として亡くなった方の財産は国庫に帰属します。しかし、家庭裁判所の審判により特別縁故者と認められることによって、その財産を取得することができます。特別縁故者とは、「被相続人と特別の関係(縁故)にあった者」を指し、その範囲は次の通りです。
 葬式費用は亡くなった人(以下、被相続人)が負担するものではありませんが、相続が発生することによって必然的に生ずる費用ですので、相続人等が負担した一定の「葬式費用」は、相続税を計算する上で、財産から控除します。
葬式費用は亡くなった人(以下、被相続人)が負担するものではありませんが、相続が発生することによって必然的に生ずる費用ですので、相続人等が負担した一定の「葬式費用」は、相続税を計算する上で、財産から控除します。
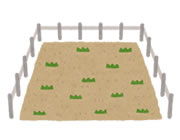 相続税を計算する際の不動産の評価額(以下、相続税評価額)は、実際に取引される価格(以下、実勢価格)より低くなる場合が多く、相続税の計算をする上においては、現金を持っているよりもメリットがある資産と考えられています。
相続税を計算する際の不動産の評価額(以下、相続税評価額)は、実際に取引される価格(以下、実勢価格)より低くなる場合が多く、相続税の計算をする上においては、現金を持っているよりもメリットがある資産と考えられています。
 夫の相続対策を検討している中で、保険会社から次の提案を受けました。これはその次の相続(二次相続)も見据えて、妻である私も生命保険に加入した方がよいというものでした。この提案はどのような効果があるのでしょうか?
夫の相続対策を検討している中で、保険会社から次の提案を受けました。これはその次の相続(二次相続)も見据えて、妻である私も生命保険に加入した方がよいというものでした。この提案はどのような効果があるのでしょうか?
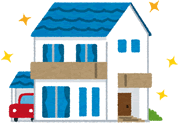 相続人の中に、生きている間に行われた贈与(以下、生前贈与)等によって、被相続人から特別に利益を得た人がいる場合は、相続開始時の財産に、その贈与によって得たものの価額を加えたものを相続財産とみなすとされています(民法第903条:以下、みなし相続財産)。その特別に得た利益のことを特別受益といい、生前贈与のうち、特別受益として認められるものは、
相続人の中に、生きている間に行われた贈与(以下、生前贈与)等によって、被相続人から特別に利益を得た人がいる場合は、相続開始時の財産に、その贈与によって得たものの価額を加えたものを相続財産とみなすとされています(民法第903条:以下、みなし相続財産)。その特別に得た利益のことを特別受益といい、生前贈与のうち、特別受益として認められるものは、



