
生命保険を信託することで、保険金の使用目的を監視させ加入者の意図を反映させることができます。
![]()
生命保険金が信託できると聞いたことがあります。それはどのような仕組みで、どのようなことができるのでしょうか?
![]()
たとえば生命保険の加入者が死後に支払われる保険金について、受取人や受取時期、使用目的などを信託制度を用いて生前に設定することで、加入者の選択の自由が広がる他、目的どおりに使われているかどうかを受託者が監視することで、より委託者の意図を反映させることができます。
![]()
1.信託の仕組みと登場人物について
◆信託とは◆
信託の定義は、信託法第2条第1項で規定しています。
■信託の仕組図
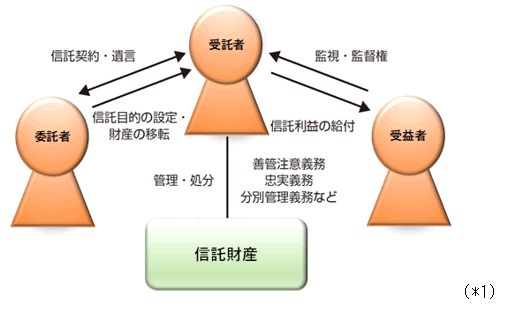
■登場人物
信託制度では、上記信託の仕組図にあるとおり、主に次の関係者が登場します。
- □委託者…信託可能な財産を受託者へ信託する者です。
- □受託者…委託者から財産を引き受け、目的に従って管理・処分する者です。
受託者は信託業の担い手であり、信託銀行、都市銀行、地方銀行等の信託業務を取扱っている金融機関、 信託会社などが該当します。(*2)
家族信託のように、親族が受託者となることもあります。
- □受益者…信託財産から生じる利益を得る人です。
受益者は誰でもなることができ、委託者自ら受益者になることもあります。
■信託の目的・財産
信託制度を利用するには、信託の“目的”や“財産”が必要です。これらは何でもよいわけではなく、違法なことや公序良俗に反することを目的にはできませんし、財産にも制限があります。
- □信託財産の例
- ・お金、株式や国債などの有価証券、土地・建物、特許権や著作権などの知的財産権など(*3)
- ・農地(農協など特定の対象が受託者となった場合(農地法第3条第2項第3号))
2.信託の例 ~高齢化への対策~
配偶者や親が高齢により物忘れがひどくなり、自分自身の財産の管理が難しくなっているときに、ご自身で財産の処分が可能な間に財産を信託し、意思能力がなくなったらできなくなる行為を受託者に託すことができます。
- □例
- ・財産にかかる契約⇒賃貸契約、売買契約、資金の借入契約 など
- ・贈与
3.生命保険の信託とは何か?
生命保険の信託とは、生命保険の加入者が死後に支払われる保険金について、受取人や受取時期などを加入者の生前に設定することができる信託契約のことをいいます。
元々の生命保険契約上で受取人を指定することは可能ですが、受取人の状況次第では加入者の意向どおりに死亡保険金が使われるとは限りません。そこで生命保険を信託することによって、加入者の意向を反映させることが可能となります。
死亡保険金を信託するときに必要となるコストは、生命保険の保険料と信託契約の諸コストです。
4.生命保険の契約と生命保険の信託契約との違い
- ■生命保険契約
生命保険契約での保険金受取人は、基本的に配偶者、子などの親族です。
- ■生命保険信託契約
生命保険信託契約では、配偶者や子など親族以外の個人や法人を保険金の受取人にすることが容易である他、受取保険金の使用目的を具体的に指定することができます。
また、受託者は目的どおりに使われているかどうかを監視します。
- ■生命保険信託のメリット、デメリット
生命保険信託の最大のメリットは、「誰に」「いつ」「どのように」保険金を渡すのか、加入者の意向によって決めることができることにあります。他方デメリットは、信託にかかる諸コストが必要となることです。
今後、生命保険信託は広がりをみせ、資産家に限らずこの制度を利用する人が増えることでしょう。
「知らなくて選択できなかった」ことと、「知っていて選択しなかった」ことは大違いです。
今後のライフプランを考える機会があれば、生命保険信託も検討してみてはいかがでしょうか。
(*1) 「金融広報中央委員会 金融なんでも百科 図表 信託のしくみ」を参考に作成
(*2) (*3) 「金融広報中央委員会 金融なんでも百科 信託」より引用
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。







 「預金等」とは
「預金等」とは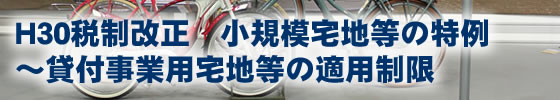
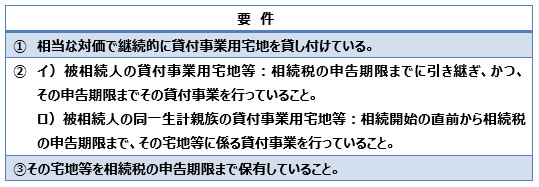
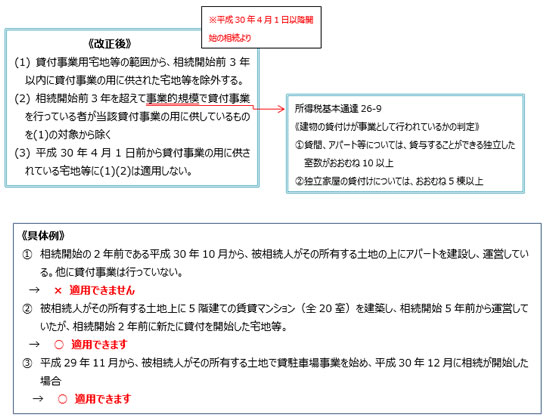

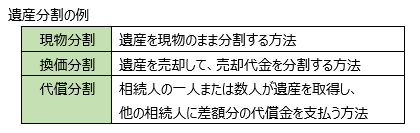

 相続放棄とは、被相続人が亡くなった後に家庭裁判所に申し立てることにより、最初から相続人でなかったこととする方法です(民法939条)。相続の放棄をすると、預金や不動産といったプラスの財産を一切引き継ぐことができなくなると同時に、借金や保証人の地位といったマイナスの財産も引き継がなくてよくなります。
相続放棄とは、被相続人が亡くなった後に家庭裁判所に申し立てることにより、最初から相続人でなかったこととする方法です(民法939条)。相続の放棄をすると、預金や不動産といったプラスの財産を一切引き継ぐことができなくなると同時に、借金や保証人の地位といったマイナスの財産も引き継がなくてよくなります。 
 家庭裁判所での遺産分割手続きには、「遺産分割調停」と「遺産分割審判」の2種類があります。
家庭裁判所での遺産分割手続きには、「遺産分割調停」と「遺産分割審判」の2種類があります。 
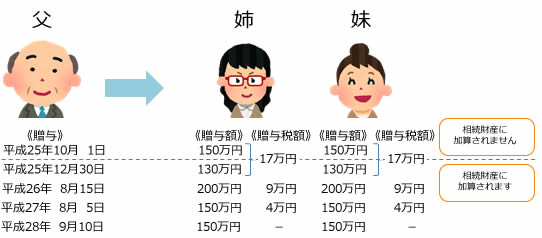
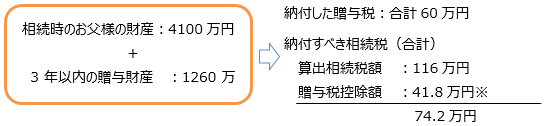

 ソシアルビル(別名:ソーシャルビル)とは、飲食店や居酒屋など複数の店舗テナントが入居するビル、いわゆる雑居ビルをいいます。特にスナックやバー、クラブなど水商売や風俗系などのテナントが入居する歓楽街にあるようなビルを指すことが多いようです。
ソシアルビル(別名:ソーシャルビル)とは、飲食店や居酒屋など複数の店舗テナントが入居するビル、いわゆる雑居ビルをいいます。特にスナックやバー、クラブなど水商売や風俗系などのテナントが入居する歓楽街にあるようなビルを指すことが多いようです。 
 ここで注意したいのは、死亡保険金は「遺産」ではなく、保険金受取人の「固有の財産」だということです。
ここで注意したいのは、死亡保険金は「遺産」ではなく、保険金受取人の「固有の財産」だということです。
 ただし、相続財産が国庫に帰属するまでには下記のように一定の手続きがあり、その手続きの中で、家庭裁判所が、相当と認める場合は「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「その他被相続人と特別の縁故があった者」(これらの者を「特別縁故者」といいます。)の請求によって、特別縁故者に対して、清算(相続債務の弁済など、下記1~4の手続き)後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる(下記5)との、特別縁故者への財産分与の手続きが定められています。
ただし、相続財産が国庫に帰属するまでには下記のように一定の手続きがあり、その手続きの中で、家庭裁判所が、相当と認める場合は「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「その他被相続人と特別の縁故があった者」(これらの者を「特別縁故者」といいます。)の請求によって、特別縁故者に対して、清算(相続債務の弁済など、下記1~4の手続き)後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる(下記5)との、特別縁故者への財産分与の手続きが定められています。 



