
離れがある場合の空き家の3,000万円控除は、敷地全体について適用できるのでしょうか?
![]()
自宅には母屋の他、子どもが独立する前に住んでいた離れがあります。この離れは現在誰も住んでおらず、放置しています。将来の私の相続を考えたとき、離れをそのままにしておいても問題ないでしょうか。現在、私は一人暮らしをしており、相続人となるであろう子どもたちはすでに全員独立して、別の場所で居を構えています。恐らく相続後に自宅を売却するのではないかと思います。
![]()
相続開始後に相続人が空き家を売却した場合には、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(以下、本制度)」という制度の適用を検討されるとよいと思います。離れがある状態でこの制度を適用する場合、不動産の建築年や取引条件が本制度の適用条件を満たしても、敷地全体のうち自宅(母屋)の床面積の占める割合についてのみ適用を受けることになり、離れの部分は適用の対象から外れます。
![]()
相続または遺贈によって被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を売却し、一定の要件に当てはまるときは(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限る)、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる制度です。
「主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物」とは、「亡くなった方の生活の本拠であった自宅」をいいます。ゆえに、自宅(母屋)以外の「離れ」は「本拠であった自宅」にあたらないため、本制度の適用を受けることはできません。
相続の開始の直前においてその土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母屋と離れなど)のある一団の土地であった場合には、その土地のうち、その土地の面積にその2以上の建築物の床面積の合計のうちに一の建築物である被相続人居住用家屋(母屋)の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限ります。
【事例の内容】
| A 敷地面積 | B 自宅(母屋)の床面積 | C 離れの床面積 |
|---|---|---|
| 1,000㎡ | 300㎡ (被相続人居住用家屋) |
200㎡ |
【計算方法】
- ① 自宅(母屋)の床面積割合計算
B 300㎡÷(B 300㎡+C 200㎡)=0.6 - ② 本制度の適用を受ける敷地面積の算出
A 1,000㎥×①で算出された割合 0.6=600㎡
この具体例の場合、敷地面積1,000㎥に対して、600㎡についてのみ本制度の適用を受けることができます。
 将来の相続においてどのような遺産分割協議が行われるか、実際にご相談者様が住んでおられる土地が売却されるか否かは不透明ですが、少なくとも本制度の適用を受ける場合に、最大限の恩恵を受けるのであれば、離れが現存のままであると、上記のように適用対象から外れてしまう部分があることにご留意ください。
将来の相続においてどのような遺産分割協議が行われるか、実際にご相談者様が住んでおられる土地が売却されるか否かは不透明ですが、少なくとも本制度の適用を受ける場合に、最大限の恩恵を受けるのであれば、離れが現存のままであると、上記のように適用対象から外れてしまう部分があることにご留意ください。
その他、具体的な本制度の適用範囲、それに伴う税金の計算についてご不明な点がありましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
<参考>
国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。







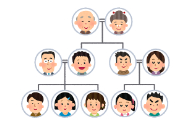 死亡保険金の受取人は、原則、「配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲内で指定する」と定めている保険会社が多いです。そのため、血縁関係のないご次男の奥様は、受取人として指定できない可能性があります。ただし、保険会社や個別事情によっては、血縁関係がない場合でも、受取人として指定できることもあるようですので、詳細は契約されている保険会社にご確認ください。
死亡保険金の受取人は、原則、「配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲内で指定する」と定めている保険会社が多いです。そのため、血縁関係のないご次男の奥様は、受取人として指定できない可能性があります。ただし、保険会社や個別事情によっては、血縁関係がない場合でも、受取人として指定できることもあるようですので、詳細は契約されている保険会社にご確認ください。
 開示請求に際し、ご相談者様を開示請求者、請求にかかる方をお母様として、今回のケースで必要となる書類は以下のとおりです。
開示請求に際し、ご相談者様を開示請求者、請求にかかる方をお母様として、今回のケースで必要となる書類は以下のとおりです。
 相続時精算課税制度とは、贈与を受けたときの贈与税の計算において、自ら選択することで適用することができる制度です。
相続時精算課税制度とは、贈与を受けたときの贈与税の計算において、自ら選択することで適用することができる制度です。
 国土交通省が公表している不動産価格指数によると、2010年を100としたマンション(全国)の価格指数は、2023年1月時点では189.4と2倍近くまで上昇しています。
国土交通省が公表している不動産価格指数によると、2010年を100としたマンション(全国)の価格指数は、2023年1月時点では189.4と2倍近くまで上昇しています。
 ①・②:被相続人である甲が負担した保険料に係る死亡保険金については、相続または遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税されます。ここでの「非課税枠」とは、死亡保険金の受取人が相続人の場合に、相続税の課税上、相続税の課税財産とみなされる死亡保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」までが非課税となる制度のことを指します。乙は甲の相続人のためこの非課税枠が適用できますが、丙は甲の相続人ではないため、非課税枠は適用できません。
①・②:被相続人である甲が負担した保険料に係る死亡保険金については、相続または遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税されます。ここでの「非課税枠」とは、死亡保険金の受取人が相続人の場合に、相続税の課税上、相続税の課税財産とみなされる死亡保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」までが非課税となる制度のことを指します。乙は甲の相続人のためこの非課税枠が適用できますが、丙は甲の相続人ではないため、非課税枠は適用できません。



