
今回は相談事例を通じて、相続の限定承認についてご紹介します。
![]()
先月、私の父が亡くなりました。相続人は私、母、妹の三人です。
相続財産は預金のみで借金は私たちが知る限りありません。しかし、父は生前に個人事業を営んでいた時期があり、その頃に相続財産である預貯金を超える借金をしていた可能性が否定できません。相続財産の範囲内で借金を返済すればよいという方法があると聞きましたが、どのような制度でしょうか。
![]()
相続が開始すると、相続人は、民法で定められている相続の方法である相続の単純承認・放棄・限定承認のうち、ひとつを選択しなければなりません。
ご質問されている相続の方法は相続の限定承認(民法第922条)と思われますので、以下相続の限定承認の制度について説明します。
![]()
 相続の限定承認とは、相続人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという相続の方法です。
相続の限定承認とは、相続人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという相続の方法です。
ご相談のように、相続をしても、プラスの財産とマイナスの財産と、どちらのほうが多いのかわからないということは十分あり、後になってから多額の借金が見つかり、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合もあります。しかし、限定承認をしていれば、相続したプラスの財産より多いマイナスの財産の部分は返さなくても良いということになります。反対に、結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かったとしても、財産はそのまま引き継げます。
限定承認を選択する場合、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に共同相続人全員で申述する必要があります(民法第915条、第923条、第924条)。
ご相談の場合、3名の相続人のうち一人でも「限定承認はしたくない」といえば、他の相続人も限定承認ができなくなります。また、相続人のうちの誰かが相続財産の一部を処分したなどの事由がある場合にも限定承認ができなくなります(民法第937条)。
なお、相続人のうちの誰かが相続放棄をした場合、その放棄をした人以外の相続人全員で限定承認の申述をすることができます。
限定承認の申述が受理された後には、相続人のうちから相続財産を管理する者が裁判所から選ばれ、その者が官報への公告、相続債権者への弁済など、一定の手続きを行うこととなります。
限定承認では、相続財産の種類等により、相続人に対し思わぬ税金が課される場合があるなど注意点が多くありますので、限定承認を検討される場合は、幣事務所までご相談ください。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。







 通常は、名義人本人が通帳、印鑑、カードなどを保管し、本人が必要とするときにいつでも解約、引出が可能です。
通常は、名義人本人が通帳、印鑑、カードなどを保管し、本人が必要とするときにいつでも解約、引出が可能です。
 「一筆の土地」とは「土地登記簿上の一個の土地」をいい、「借地権」とは「建物を建てるために地代を払って他人から土地を借りる権利」をいいます。
「一筆の土地」とは「土地登記簿上の一個の土地」をいい、「借地権」とは「建物を建てるために地代を払って他人から土地を借りる権利」をいいます。
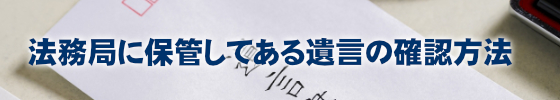
 【1】遺言書が保管されているかの確認
【1】遺言書が保管されているかの確認
 お父様が亡くなった時点で所有していた財産で、金銭的に価値のある全ての財産に対して相続税が課税されます。具体的には、土地、建物、借地権(土地を借りる権利)、事業用(農業用)の財産、株式、公社債、投資信託、現預金、貸付金、家庭用財産(家電、家具など)、書画骨とう、貴金属、自動車、特許権、電話加入権、立木などが該当します。
お父様が亡くなった時点で所有していた財産で、金銭的に価値のある全ての財産に対して相続税が課税されます。具体的には、土地、建物、借地権(土地を借りる権利)、事業用(農業用)の財産、株式、公社債、投資信託、現預金、貸付金、家庭用財産(家電、家具など)、書画骨とう、貴金属、自動車、特許権、電話加入権、立木などが該当します。
 共有を解消するための具体的な方法としては、下記が考えられます。
共有を解消するための具体的な方法としては、下記が考えられます。


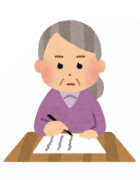 1.共同遺言の禁止
1.共同遺言の禁止



