
廃業後空室のままの修繕が必要な自社ビルを、相続財産として子供に託すのは忍びないのですが、どうしたらよいでしょうか。
![]()
少し前に会社を廃業し、会社に賃貸していた私所有の築40年のビルが未使用となっています。賃貸を検討していますが、修繕が必要となるため迷っています。このままの状態で相続になったときに、子供たちに迷惑がかかるため何とかしたいと考えていますが、どうしたらよいでしょうか。なお、借入金はありません。
![]()
空きビルの活用法としては、賃貸や売却などが考えられますが、将来の相続を見据えるのであれば、ご自身のみで判断するのではなく、お子様等に相談しながら検討されることをおすすめします。
![]()
 1.元自社ビルを賃貸する場合
1.元自社ビルを賃貸する場合自社で使用していたビルは、フロア単位での賃貸が難しく、一棟での賃貸となるケースが多いです。一棟で賃貸する場合、管理面の負担は少なくなりますが、需要が限定され、借主がなかなか見つからない恐れがあります。
更に、オフィスは、マンション等の住居よりもエリアが限定されるため、立地によっては、フロア単位での賃貸が可能であっても借主がなかなか見つからない場合があります。
その一方で、事前に必要となる修繕の費用は、少なくても想定賃料の1年分以上と推定されますので、修繕実施の有無及びその実施時期については、慎重に検討する必要があります。
しかし、検討に時間をかけ過ぎますとその間の維持管理費(固定資産税・火災保険料 等)の負担が重くのしかかってきます。
以下の前提条件で、①ビルを賃貸している場合、②ビル解体後更地のままの場合、③空きビルのままの場合、それぞれの相続税評価額を算定してみましょう。
土地 路線価:200千円/㎡ 面積:500㎡ 借地権割合:50%
建物 固定資産税評価額 50,000千円 借家権割合:30% 賃貸割合:100%
| ①ビルを賃貸している場合 | ②ビル解体後更地のままの場合 | ③空きビルのままの場合 | |
|---|---|---|---|
| 土地 | 200千円×500㎡=100,000千円 100,000千円-100,000千円×50%×30%×100%=85,000千円 |
200千円×500㎡=100,000千円 | 200千円×500㎡=100,000千円 |
| 建物 | 50,000千円-50,000千円×30%×100%=35,000千円 | ― | 50,000千円 |
| 合計 | 85,000千円+35,000千円=120,000千円 | 100,000千円 | 100,000千円+50,000千円=150,000千円 |
上記のとおり、相続税評価額は、最も収支が悪い(マイナス)空きビルが最も高額となります。
上記2.のとおり、空きビルの状態は1日も早く解消する必要があります。その対策として、以下をおすすめします。
- ①不動産仲介業者等に相談し、所有ビルの賃貸需要を把握
- ②賃貸需要が見込めない場合は、現状での売却又はビル解体後の活用・売却を検討
- ③賃貸需要が見込める場合は、期間を設けて賃貸募集を開始
- 旺盛な需要が見込める場合は、賃貸募集前の修繕実施も検討
- 安価な賃料での賃貸は、所有ビルの価値減少に繋がるため、適正賃料での賃貸を心掛ける
- ④期間内に借主が見つからない場合は、②を検討
なお、将来の相続を見据えた所有ビルの活用については、ご自身のみの判断で決定するのではなく、お子様等に相談されながら検討されることをおすすめします。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。







 プランA・Bいずれも確実に妹さんが保険金を受け取れますが、税務上の取扱いや特徴が異なります。どちらが適しているかは、相談者ご自身の財産の保有状況が重要なポイントとなります。
プランA・Bいずれも確実に妹さんが保険金を受け取れますが、税務上の取扱いや特徴が異なります。どちらが適しているかは、相談者ご自身の財産の保有状況が重要なポイントとなります。
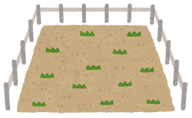 相続人がおらず、財産が相続債権者や受遺者にも帰属せず、特別縁故者がいない場合には、相続財産は国庫に帰属する(民法959条)とされています。
相続人がおらず、財産が相続債権者や受遺者にも帰属せず、特別縁故者がいない場合には、相続財産は国庫に帰属する(民法959条)とされています。
 農地は、農地法などの法律により宅地への転用が制限されています。
農地は、農地法などの法律により宅地への転用が制限されています。
 不動産に関する権利は、民法第177条により、登記をしなければ第三者に対して主張(対抗)できないことになっています。
不動産に関する権利は、民法第177条により、登記をしなければ第三者に対して主張(対抗)できないことになっています。


 ご本人が意思表示できないのであれば、後見人を付すなどして、ご本人の代わりに意思表示をしてもらうことが考えられますが、本件でそのためだけに後見人等を選任するのは、いささか躊躇します。後見人は登記以外の日常的な財産管理等もするため、きっかけが登記であっても、かなり煩雑で厳格な手続きをし続ける必要があるためです。
ご本人が意思表示できないのであれば、後見人を付すなどして、ご本人の代わりに意思表示をしてもらうことが考えられますが、本件でそのためだけに後見人等を選任するのは、いささか躊躇します。後見人は登記以外の日常的な財産管理等もするため、きっかけが登記であっても、かなり煩雑で厳格な手続きをし続ける必要があるためです。

 原野商法とは、値上がりの見込みのほとんどない山林や原野を、「将来、確実に値上がりする」などと勧誘し、不当に購入させるもので、1970年~1980年代に多発した問題のある商法です。
原野商法とは、値上がりの見込みのほとんどない山林や原野を、「将来、確実に値上がりする」などと勧誘し、不当に購入させるもので、1970年~1980年代に多発した問題のある商法です。



